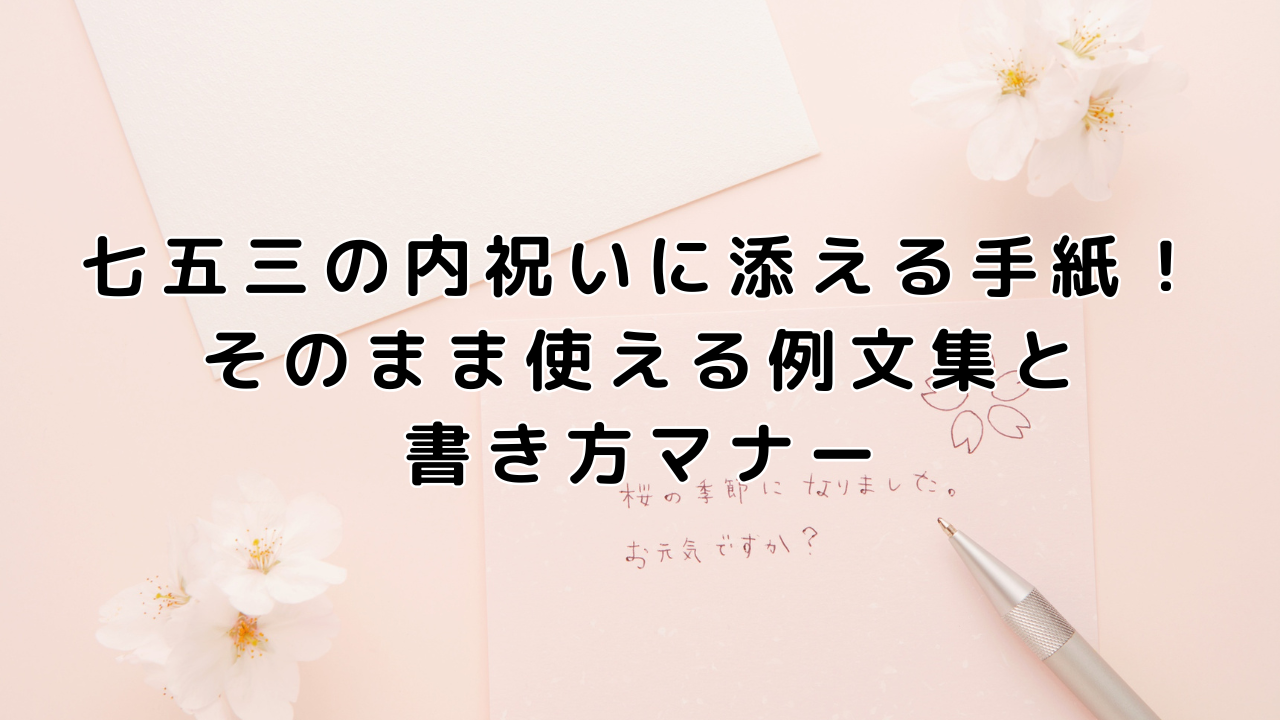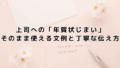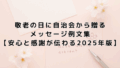七五三のお祝いをいただいたとき、「どんな手紙を添えればいいのだろう?」と迷う方は多いものです。
内祝いの品物だけでも十分ですが、そこに一通の手紙を添えるだけで、感謝の気持ちがより深く伝わります。
本記事では、七五三の内祝いに添える手紙の基本的な書き方やマナーをわかりやすく整理しました。
さらに、そのまま使えるフルバージョン例文を祖父母・友人・ビジネス関係者など相手別にたっぷり掲載しています。
フォーマルからカジュアルまで幅広く揃えているので、状況に合わせて選べば安心です。
七五三という子どもの成長を祝う大切な節目に、心を込めたお礼状を届けたい方は、ぜひ参考にしてください。
七五三の内祝いに添える手紙とは?
七五三の内祝いは、ただ品物を贈るだけでなく、そこに添える「手紙」がとても大きな意味を持ちます。
ここでは、七五三における内祝いの手紙がどんな役割を果たすのかを見ていきましょう。
七五三の内祝いの意味と手紙の役割
七五三は、子どもの成長を感謝し、これからの健やかな未来を願う日本の伝統行事です。
その節目にお祝いをいただいた場合には「内祝い」としてお返しをするのがマナーとされています。
そして、内祝いの品物に感謝の気持ちを言葉で添える手紙を加えることで、形式だけではなく心からのお礼を伝えることができます。
これは、贈り物が物理的な「お返し」なのに対し、手紙は気持ちの「橋渡し」のような役割を果たすといえるでしょう。
| 手紙を添えるメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 感謝が伝わりやすい | 「ありがとう」の気持ちが直接的に届く |
| 相手との関係が深まる | 形式的なお返しより温かみが感じられる |
| 子どもの成長を報告できる | 写真やエピソードを添えて近況を共有できる |
感謝の気持ちを伝える手紙が喜ばれる理由
人は、物をもらったこと以上に「気持ちを向けてもらったこと」に心を動かされます。
例えば同じお菓子の詰め合わせでも、そこに直筆で丁寧に綴られたお礼状が添えられていると、受け取る側は「自分を大切に思ってくれている」と感じられるのです。
つまり、七五三の内祝いの手紙は、贈り物を「ただのお返し」から心のこもった記念の贈り物へと格上げしてくれる存在といえるでしょう。
七五三内祝いの手紙を書くときの基本マナー
七五三の内祝いに添える手紙は、相手との関係性やタイミングを意識して書くことが大切です。
ここでは、手紙を書くうえで押さえておきたい基本マナーを整理していきましょう。
送るタイミングと適切な文体
七五三の内祝いの手紙は、なるべくお参りを終えてから1か月以内に送るのが理想です。
あまり遅くなると感謝の気持ちが薄れて伝わってしまうので注意しましょう。
また、相手との関係性によって文体を変えるのもポイントです。
| 相手 | 適した文体 | 注意点 |
|---|---|---|
| 祖父母・親戚 | ややフォーマル | 子どもの成長を具体的に書くと喜ばれる |
| 友人・知人 | カジュアル〜丁寧 | 親しみを込めつつも礼儀は忘れない |
| ビジネス関係者や上司 | フォーマル | 崩れすぎた表現は避ける |
必ず入れるべき内容(子どもの名前・成長の様子など)
どのような相手に対しても、以下の要素は必ず含めるようにしましょう。
- いただいたお祝いへの感謝
- 子どもの名前と年齢(「おかげさまで〇歳になりました」など)
- 七五三を無事に迎えられたこと
- 内祝いの品を贈ったこと
- 相手の健康や幸せを祈る一言
これらを押さえておけば、失礼なく気持ちの伝わる手紙になります。
避けたいNG表現
せっかくの手紙でも、言葉の選び方を間違えると相手に違和感を与えてしまいます。
例えば「ついでに送ります」など、軽すぎる表現は絶対に避けましょう。
また「お返しします」という言葉も、内祝いではNGワードです。
代わりに「感謝の気持ちを込めて」「ささやかですが」といった表現を使うと柔らかい印象になります。
つまり、七五三内祝いの手紙は感謝を伝えることに全力を注ぐのが最大のマナーなのです。
七五三内祝いの手紙の基本構成と書き方
いざ手紙を書こうと思っても、「どんな流れで文章を組み立てればよいの?」と迷う方も多いですよね。
ここでは、七五三内祝いの手紙をスムーズに書けるよう、基本の構成と書き方を順番に解説します。
冒頭の挨拶・時候の挨拶
まずは冒頭で季節感のある挨拶を入れましょう。
例えば「秋風が心地よい季節となりましたが」「寒さが一段と増してまいりましたが」といったフレーズです。
これは単なる形式ではなく、相手を思いやる気持ちを示す大切な一文です。
お祝いへのお礼を伝える
いただいたお祝いに対して感謝の言葉をしっかり述べましょう。
「心のこもったお祝いをいただき誠にありがとうございました」といった丁寧な言葉がベストです。
相手との関係が近ければ「ありがとう!」でも問題ありません。
七五三を無事に迎えた報告
次に、子どもが七五三を無事に迎えられたことを伝えます。
「おかげさまで元気に七五三を迎えることができました」「晴れ着姿で嬉しそうにしておりました」など、ちょっとしたエピソードを入れると温かみが増します。
内祝いの品を伝える言葉
贈り物を送った場合は、その旨を明記しましょう。
「ささやかですが、感謝の気持ちを込めて品をお送りしました」といった表現が一般的です。
ここで「お返しします」とは書かないように注意してください。
結びの挨拶と署名
最後は相手の健康や幸せを祈る言葉で締めくくります。
「皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします」「どうぞお体に気をつけてお過ごしください」といった一文が定番です。
そして、日付と署名を忘れずに書きましょう。
| 構成の流れ | 例文フレーズ |
|---|---|
| 冒頭の挨拶 | 「秋風が心地よい季節となりましたが〜」 |
| お祝いのお礼 | 「心のこもったお祝いをいただき誠にありがとうございました」 |
| 子どもの成長報告 | 「おかげさまで元気に七五三を迎えることができました」 |
| 内祝い品の案内 | 「ささやかですが感謝の気持ちを込めて品をお送りしました」 |
| 結びの挨拶 | 「皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします」 |
この流れを押さえておけば、自然で丁寧な手紙が完成します。
七五三内祝いの手紙 例文集(関係性別)
ここからは実際に使える例文を関係性ごとにまとめました。
フォーマルからカジュアルまで、そのまま使えるフルバージョン例文も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
祖父母・親戚向けのフルバージョン例文
もっとも丁寧さが求められるのが祖父母や親戚への手紙です。
子どもの成長を具体的に伝えると喜ばれます。
――例文――
拝啓 秋も深まり、朝晩の冷え込みが感じられる季節となりました。
おじい様、おばあ様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
このたびは、〇〇(子どもの名前)の七五三に際しまして、心温まるお祝いをいただき誠にありがとうございました。
おかげさまで〇〇もすくすくと成長し、元気に七五三を迎えることができました。
当日は晴れ着姿でにこやかに参拝し、その姿を見て私たちも胸がいっぱいになりました。
ささやかではございますが、感謝の気持ちを込めて内祝いの品をお贈りいたします。
どうぞご笑納くださいませ。
皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
まずは書中にて御礼申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇(送り主名)
友人・知人向けのフルバージョン例文
一般的な友人や知人には、かしこまりすぎず、程よく丁寧な文調がおすすめです。
――例文――
拝啓 爽やかな秋風が心地よい季節となりましたが、〇〇様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたびは、〇〇の七五三に際しまして温かいお祝いをいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで無事にお参りを済ませることができ、家族一同心より感謝しております。
つきましては、感謝の気持ちを込めてささやかな品をお贈りいたしますので、どうぞお納めください。
季節柄、体調を崩しやすい時期ですので、どうぞご自愛くださいませ。
まずは書面にて御礼申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇
親しい友人へのカジュアルな例文(短文・LINE風)
親しい友人へのお礼なら、少しラフな調子でも大丈夫です。
LINEやメッセージカードに使える例文を紹介します。
- 「七五三のお祝いありがとう!無事に参拝できて家族みんなで喜んでいます。感謝の気持ちを込めてちょっとした品を送ります。これからも〇〇の成長を見守ってね。」
- 「お祝いありがとう!写真を同封するのでぜひ見てね。元気に育ってます!」
ビジネス関係者や目上の方への丁寧な例文
会社の上司やお世話になっている方への手紙は、フォーマルな表現を徹底しましょう。
――例文――
拝啓 晩秋の候、〇〇様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびは、〇〇の七五三に際しまして格別のお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます。
おかげさまで無事に七五三を迎えることができ、心より感謝いたしております。
ささやかではございますが、内祝いの品をお贈りいたしますので、何卒ご笑納くださいませ。
末筆ながら、〇〇様のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇
| 相手 | おすすめの文調 | ポイント |
|---|---|---|
| 祖父母・親戚 | フォーマル寄り | 成長エピソードを具体的に入れる |
| 友人・知人 | やや丁寧 | 「ありがとう」の気持ちを中心に |
| 親しい友人 | カジュアル | 短文やLINE風でもOK |
| ビジネス関係者 | フォーマル | 敬語を崩さない |
七五三内祝いの手紙 追加の例文集(場面別)
相手との関係だけでなく、贈るシーンによって文章を少し工夫するとより気持ちが伝わります。
ここでは「写真を添える場合」「内祝い品を強調したい場合」「遠方の相手に送る場合」の3つのシーンに合わせた例文をご紹介します。
写真を添える場合の例文
七五三の写真を同封する場合は、そのことを一言添えると親切です。
――例文――
拝啓 日ごとに秋が深まってまいりましたが、〇〇様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
このたびは、〇〇の七五三に際しまして温かなお祝いをいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで無事に成長し、この日を迎えることができました。
晴れ着姿の写真を同封いたしますので、ご覧いただければ幸いです。
感謝の気持ちを込めて、ささやかではございますが品をお贈りいたします。
今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。
敬具
内祝い品を強調したい場合の例文
贈り物そのものに思いを込めたいときは、品物のことを具体的に書きましょう。
――例文――
拝啓 紅葉の美しい季節となりました。
このたびは、〇〇の七五三のお祝いをいただき、心より感謝申し上げます。
内祝いとして、〇〇様のお好きなお菓子を選びました。
ささやかではありますが、感謝の気持ちが伝われば幸いです。
これからも〇〇の成長を見守っていただけますと幸いです。
まずは書中にて御礼申し上げます。
敬具
遠方の相手への例文
なかなか会えない遠方の親戚や知人には、近況を少し詳しく伝えると喜ばれます。
――例文――
拝啓 木々の葉も色づき始め、秋の深まりを感じる季節となりました。
ご無沙汰しておりますが、〇〇様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。
このたびは、〇〇の七五三に際しましてお祝いを賜り、誠にありがとうございました。
〇〇も元気に成長し、無事に七五三を迎えることができました。
日頃の様子を少しでもお伝えしたく、写真を同封いたしました。
遠方でなかなかお会いできませんが、またお会いできる日を家族一同楽しみにしております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
敬具
| シーン | 工夫ポイント | おすすめ表現 |
|---|---|---|
| 写真を添える | 「同封いたしますのでご覧ください」 | 成長の様子を具体的に伝える |
| 品物を強調する | 「お好きなものを選びました」 | お返しではなく感謝の贈り物 |
| 遠方の相手へ | 「ご無沙汰しております」「写真を同封しました」 | 近況をやや詳しく書く |
七五三内祝いの手紙に写真や品物を添える工夫
七五三の内祝いでは、手紙と一緒に写真や品物を添えることで、より気持ちが伝わりやすくなります。
ここでは、写真や内祝い品を選ぶときの工夫や、メッセージに添えるときの注意点をご紹介します。
写真を同封するときのマナー
七五三は子どもにとっても家族にとっても大切な節目なので、写真を同封すると相手にとても喜ばれます。
ただし、写真は自己満足にならないよう注意が必要です。
「一番お気に入りの1〜2枚」を選び、封筒に折れないよう台紙を添えると丁寧です。
手紙の中では「晴れ着姿の写真を同封いたしましたのでご覧いただければ幸いです」と一言添えましょう。
おすすめの内祝い品とメッセージ例
内祝いの品物は相手のライフスタイルや好みに合わせるのが基本です。
どれを選ぶか迷ったら、消耗品や日常使いしやすい品が安心です。
| 品物の例 | 特徴 | 添えるメッセージ例 |
|---|---|---|
| お菓子・スイーツ | 幅広い年代に喜ばれる定番 | 「皆さまで召し上がっていただければ嬉しいです」 |
| タオル・日用品 | 実用性が高く、気軽に贈れる | 「日々お使いいただければ幸いです」 |
| お茶やコーヒーセット | 年配の方にも好まれやすい | 「おくつろぎのひとときにお楽しみください」 |
| ちょっとした小物や雑貨 | 相手の趣味に合わせやすい | 「ささやかですが気に入っていただければ嬉しいです」 |
このように、品物と一緒にひとことメッセージを添えるだけで、贈り物の印象がぐっと温かいものになります。
まとめ|心を込めた七五三内祝いの手紙で感謝を伝えよう
七五三の内祝いに添える手紙は、単なる形式的なものではなく、相手に感謝の気持ちをしっかり伝える大切な役割を担っています。
この記事でご紹介した例文やポイントを参考にすれば、どんな相手にも失礼なく、温かい手紙を書くことができます。
七五三内祝いの手紙で大切にしたいポイント
最後に、手紙を書く際に押さえておきたいポイントをもう一度整理しておきましょう。
| 要素 | 意識すること |
|---|---|
| タイミング | 七五三後、できれば1か月以内に送る |
| 文体 | 相手との関係性に合わせてフォーマル〜カジュアルに調整 |
| 内容 | お祝いへの感謝・子どもの成長・内祝い品について必ず触れる |
| 避けたい表現 | 「お返しします」「ついでに送ります」など |
| プラスα | 写真やエピソードを添えるとより喜ばれる |
手紙は長さよりも気持ちが込められているかが一番大切です。
フォーマルな文例を参考にしてもよいですし、親しい相手にはシンプルに「ありがとう」を伝えるだけでも十分です。
心を込めた一通が、相手にとって忘れられない贈り物になるでしょう。