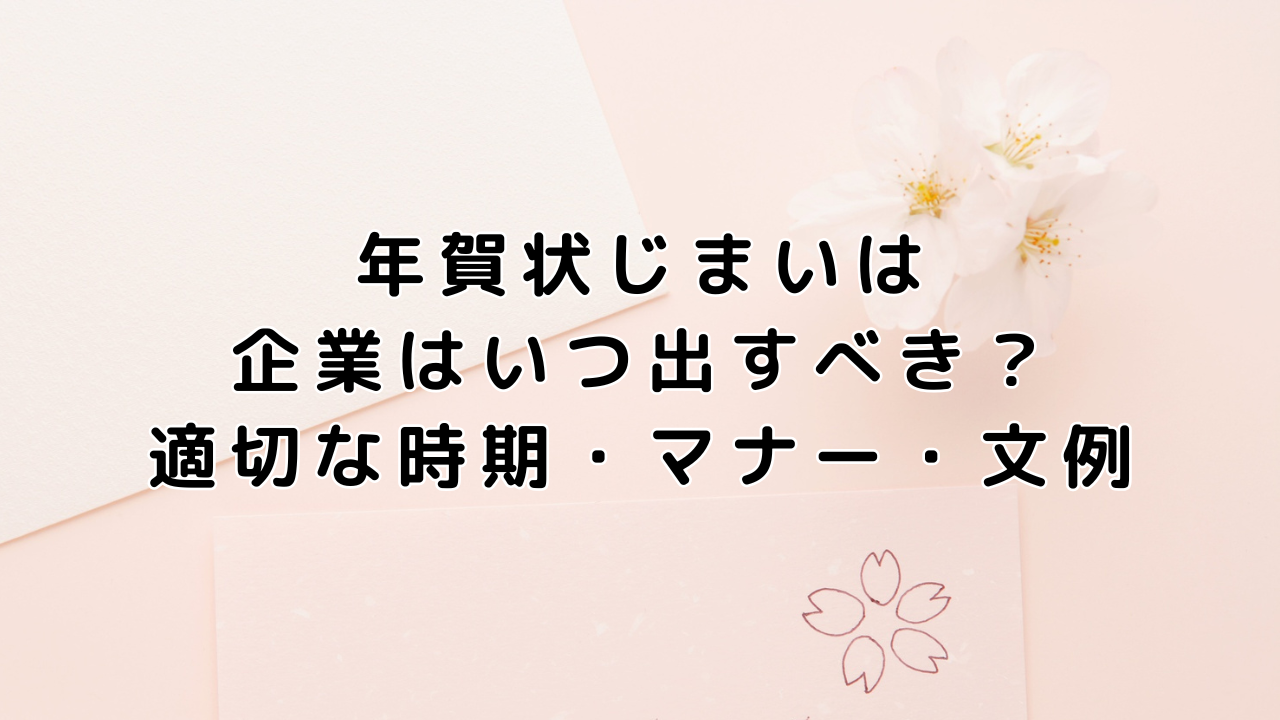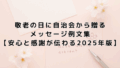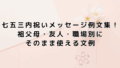2025年、企業間で「年賀状じまい」が一気に広がっています。
背景には郵便料金の値上げやデジタル化の進展、さらにはSDGsへの配慮といった社会的な要因があります。
しかし、いざ「やめる」と決めても、取引先や顧客に対していつ・どのように通知すれば失礼にならないのか、迷う担当者は少なくありません。
本記事では、企業が年賀状じまいを行う際の適切な時期(11月〜12月初旬)、遅れた場合の対処法、通知方法とマナーをわかりやすく解説します。
さらに、取引先・顧客・社内などシーン別に使える文例も紹介。
「企業らしいご挨拶の形」を選び、新しい年始文化を築くための実践的なヒントをまとめています。
これから年賀状じまいを検討する企業担当者にとって、必ず役立つ内容です。
企業の年賀状じまいが広がる背景とは
まずは、なぜ今「企業の年賀状じまい」が広がっているのかを見ていきましょう。
郵便料金の値上げやデジタル化、さらにはSDGsの浸透といった社会背景が大きく関係しています。
ここでは、最新の調査データをもとに、その流れを整理してみます。
最新調査でわかる年賀状じまいの普及率
帝国データバンクの調査によると、2025年時点で年賀状じまいを行った企業は約半数に達しています。
具体的には、年賀状じまいをした企業が49.4%、継続して送る企業は34.4%と報告されています。
つまり、すでに3社に1社しか年賀状を出していない状況なのです。
| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 年賀状じまいをした企業 | 49.4% |
| 年賀状を継続する企業 | 34.4% |
| その他(検討中など) | 16.2% |
郵便料金値上げやSDGsが後押しする理由
2025年10月からの郵便料金値上げ(1枚85円)は、多くの企業にとって直接的な負担増となりました。
さらに「ペーパーレス化」や「環境保護」を重視する社会の流れも、年賀状じまいを後押ししています。
特にSDGsを掲げる企業にとっては、紙の使用を減らすことが企業姿勢を示すアクションにもなるのです。
年賀状を継続する企業の考え方
一方で、年賀状をやめない企業も四分の一ほど存在します。
その理由には、「日本文化の継承」「人間味のある関係維持」といった価値観があります。
つまり、年賀状じまいは一律の正解があるわけではなく、企業ごとの理念や取引先との関係性が大きく影響しているのです。
企業が年賀状じまいを決めるメリットとデメリット
次に、企業が年賀状じまいを選ぶことで得られるメリットと、反対に気をつけたいデメリットを整理します。
単なるコスト削減にとどまらず、業務効率化や企業イメージの向上につながる一方で、失われる“人間味”も無視できません。
コスト削減・業務効率化などのメリット
年賀状を廃止する最大のメリットは、やはりコスト削減です。
郵便料金だけでなく、印刷費、社員の作業時間といった見えにくいコストも大幅に軽減できます。
また、年末の繁忙期に作業を削減できることで、事務効率化にも直結します。
| 削減できるコスト項目 | 具体例 |
|---|---|
| 郵便料金 | 1枚85円 × 取引先数 |
| 印刷・デザイン費用 | 外注費や社内印刷代 |
| 人件費 | 社員の宛名入力や仕分け作業時間 |
取引先との関係性に与える影響
一方で、年賀状じまいは取引先との距離感に影響を与える可能性があります。
「年賀状をいただいて嬉しかった」という感覚は、紙の年賀状特有の温かみです。
そのため、一部の企業では「形式的でも続けるべき」と考えるところも少なくありません。
デジタル化で新しく生まれる交流手段
ただし、年賀状をやめた企業の多くは、メールやSNSに切り替えることで「返信が早い」「双方向のやりとりができる」といったメリットを実感しています。
たとえば、SNSでの新年挨拶は写真や動画を交えて投稿でき、従来のハガキにはない魅力を発揮します。
つまり、年賀状じまいは単なる“削減”ではなく、新しいコミュニケーションの扉を開くきっかけにもなり得るのです。
年賀状じまいのお知らせはいつ出すのが適切か
「年賀状じまい」は、伝えるタイミングによって相手の受け取り方が大きく変わります。
ここでは、企業が通知を出すべき時期と、遅れてしまった場合の対応、さらに節目の年に合わせた実施例を紹介します。
企業が通知する最適な時期(11月〜12月初旬)
最も一般的なのは、取引先が年賀状を準備する前の11月から12月初旬です。
この時期であれば、相手が年賀状リストに名前を載せる前に知らせることができ、無駄を防げます。
12月中旬以降は避けるのがマナーとされ、遅れると相手がすでに印刷・投函を済ませている場合もあるため注意が必要です。
| 時期 | 適切さ | ポイント |
|---|---|---|
| 11月上旬〜12月初旬 | 最適 | 相手の準備前。双方にとって効率的。 |
| 12月中旬〜下旬 | 遅い | 相手がすでに作業済みの可能性大。 |
| 年明け以降 | 不適切 | 寒中見舞いなどで代替する必要あり。 |
遅れた場合の対応と注意点
12月中旬を過ぎてしまった場合は、通常の年賀状を作成し、その最後に「来年から辞退します」と一文を添える方法が推奨されます。
特に取引先や目上の相手には、簡潔であっても感謝の言葉を加えることが大切です。
また、手書きで一文を添えると、形式的になりすぎず誠意が伝わります。
節目のタイミング(退職・周年・祝い年)での実施も有効
通知時期は年末だけでなく、企業や担当者の節目に合わせても自然です。
例えば「会社の創立○周年」「代表交代」「定年退職」などの節目に合わせると、相手にとっても納得感があります。
個人の場合でも、還暦や古希といった祝い年を理由にすれば、失礼にならずスムーズに伝えられるでしょう。
企業における年賀状じまいの通知方法とマナー
年賀状じまいをスムーズに進めるためには、通知方法の選び方とマナーが重要です。
形式的に済ませるのではなく、相手に配慮しながら伝えることが、関係維持のポイントになります。
最後の年賀状に一文を添える方法
最も自然で無難なのが、通常の年賀状を作成し、最後に「来年からは年賀状を控えさせていただきます」と添えるやり方です。
この方法は、従来通りの年賀状の流れを崩さず、相手に唐突な印象を与えません。
特に不特定多数の相手に伝える場合には「どなた様とも年賀状は控えさせていただきます」と表現するのが良いでしょう。
| 通知の仕方 | 特徴 |
|---|---|
| 最後の年賀状に一文を添える | 最も自然で失礼がない方法 |
| 単独で通知する(挨拶状) | フォーマル度が高く、重要取引先に向いている |
| メールやSNSで通知 | 親しい関係性の相手に限定して有効 |
メール・SNS・電話での伝え方
普段からメールやSNSでやり取りがある取引先や顧客には、これらの手段での通知も自然です。
ただし、ビジネス上のフォーマルな関係にある相手に対しては、メールだけで済ませるのは不十分とされます。
必要に応じて「挨拶状」や「年賀状+一文」と組み合わせることで、誠意を示せます。
目上や重要取引先への正式通知の注意点
特にお世話になっている相手や目上の立場の方へは、正式な書面で通知するのが安心です。
社外向けの挨拶状には、定型の敬語を用いながら「感謝」と「今後の関係継続」を必ず盛り込みましょう。
例えば、「今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」といったフレーズを添えると、形式的でなく真心を感じさせる通知になります。
企業で使える年賀状じまいの文例集
ここからは、実際に使える「年賀状じまい」の文例を紹介します。
取引先・顧客・社内・環境配慮型など、相手や状況に合わせて活用できる形にまとめました。
取引先向けのフォーマル文例
取引先には、フォーマルな言葉遣いで感謝を伝えることが重要です。
文末には「今後ともよろしくお願いいたします」と添えることで、関係を続けたい意志を示せます。
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社では2025年の年賀状をもちまして、年賀状によるご挨拶を控えさせていただくこととなりました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
顧客向けの親しみやすい文例
顧客にはやや柔らかいトーンが向いています。
「ご愛顧」という言葉を添えると自然です。
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
勝手ながら、本年をもちまして年賀状でのご挨拶は控えさせていただきます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
社内向け(上司・同僚)文例
社内向けはカジュアルで問題ありません。
ただし、上司には敬語を残すのがベターです。
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
誠に恐縮ですが、本年をもちまして年賀状によるご挨拶を控えさせていただきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
環境配慮・SDGsを強調する場合の文例
環境配慮を理由にする場合は、企業姿勢を示す良い機会にもなります。
「持続可能性」や「環境負荷低減」という表現を添えると説得力が増します。
平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では、環境負荷低減およびSDGsの取り組みの一環として、来年度より年賀状によるご挨拶を控えさせていただくこととなりました。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
| 相手 | 文例の特徴 |
|---|---|
| 取引先 | 格式を重視し、敬語を徹底 |
| 顧客 | 親しみを込めつつ感謝を表現 |
| 社内 | 簡潔でややカジュアルな表現 |
| 環境配慮型 | SDGsや企業姿勢をアピール |
年賀状じまいを円滑に進めるポイント
「年賀状じまい」は、ただやめると伝えるだけでは不十分です。
相手に不快感を与えず、むしろ信頼関係を強めるための工夫が欠かせません。
ここでは、円滑に進めるための具体的なポイントを解説します。
配慮した表現と感謝の気持ちの伝え方
通知の際には「辞退」「控える」「ご理解を賜りたい」といった柔らかい表現を選ぶことが大切です。
また、これまでの交流への感謝の言葉を必ず添えましょう。
「長年のご厚情に心より感謝申し上げます」といった一文を入れるだけで、印象が大きく変わります。
代替の挨拶手段を提示するメリット
「今後はメールやSNSでご挨拶させていただきます」と伝えると、関係が途切れにくくなります。
さらに、企業の場合は自社のHPに新年の挨拶ページを設け、そこに案内するのも効果的です。
年賀状じまいをきっかけに、より効率的で双方向的な交流に移行できるのです。
| 代替手段 | 特徴 |
|---|---|
| メール | ビジネスに適したフォーマルな方法 |
| SNS | 気軽でリアルタイムな交流が可能 |
| 自社HP | 企業姿勢を示し、広く周知できる |
トラブルを防ぐための実践的アドバイス
急にやめると「なぜ自分だけに出さないのか」と誤解を招くことがあります。
そのため「どなた様にも控えさせていただきます」と明記し、平等に扱っていることを伝えるのが大切です。
さらに、重要な取引先には別途電話やメールでフォローすると、より円滑な移行が可能になります。
今後の企業における年賀状じまいの展望
ここまで見てきたように、年賀状じまいは単なる流行ではなく、社会全体の変化を映す動きです。
今後、さらに多くの企業が年賀状を控える一方で、伝統を大切にする企業も一定数残り続けると考えられます。
デジタル挨拶の普及と新しい文化の形成
メールやSNS、自社サイトなど、デジタルでの新年挨拶はますます一般化していきます。
特にSNSでは、画像や動画を交えて挨拶できるため、従来のはがきより表現の幅が広がるという利点があります。
また、オンライン会議や動画メッセージを新年の挨拶に取り入れる企業も増えるでしょう。
| 挨拶手段 | 特徴 |
|---|---|
| メール | フォーマルさを保ちながら効率的 |
| SNS | 双方向の交流が可能。拡散力が高い |
| 動画メッセージ | 臨場感があり、記憶に残りやすい |
年賀状を残す企業が示す伝統的価値
一方で、今後も年賀状を継続する企業も存在します。
そこには「日本文化の継承」「心を込めたやり取り」という価値観が根付いています。
また、紙の年賀状は手元に残りやすく、形式的であっても相手を大切に思っている証と受け止められることもあります。
まとめ:企業が選ぶべきこれからの姿勢
結論として、年賀状じまいに正解はありません。
重要なのは、企業の理念や取引先との関係性に合わせて「どのように挨拶を届けるか」を選ぶことです。
年賀状をやめるにせよ続けるにせよ、その背景にある配慮と真心が相手に伝われば、関係は良好に保たれるでしょう。
まとめ
2025年現在、企業の間で「年賀状じまい」は急速に広がっています。
背景には、郵便料金の値上げやデジタル化、さらにはSDGsへの取り組みなど、社会全体の変化があります。
お知らせのタイミングは11月〜12月初旬が理想的で、遅れた場合は年賀状に一文を添える方法が適切です。
通知方法は、最後の年賀状・メールやSNS・正式な挨拶状など、相手との関係性に応じて選びましょう。
また、配慮した表現や感謝の言葉を添え、メールやSNSなどの代替手段を提示することで、円滑に移行できます。
企業にとって年賀状じまいは、単なる「やめる」選択ではなく、新しいコミュニケーションを築く機会です。
今後は、紙の年賀状を続ける企業とデジタル化に舵を切る企業が共存していくでしょう。
大切なのは形式そのものではなく、相手への心遣いをどう伝えるかという姿勢です。
年賀状じまいを通じて、自社らしいご挨拶のスタイルを見直してみてはいかがでしょうか。