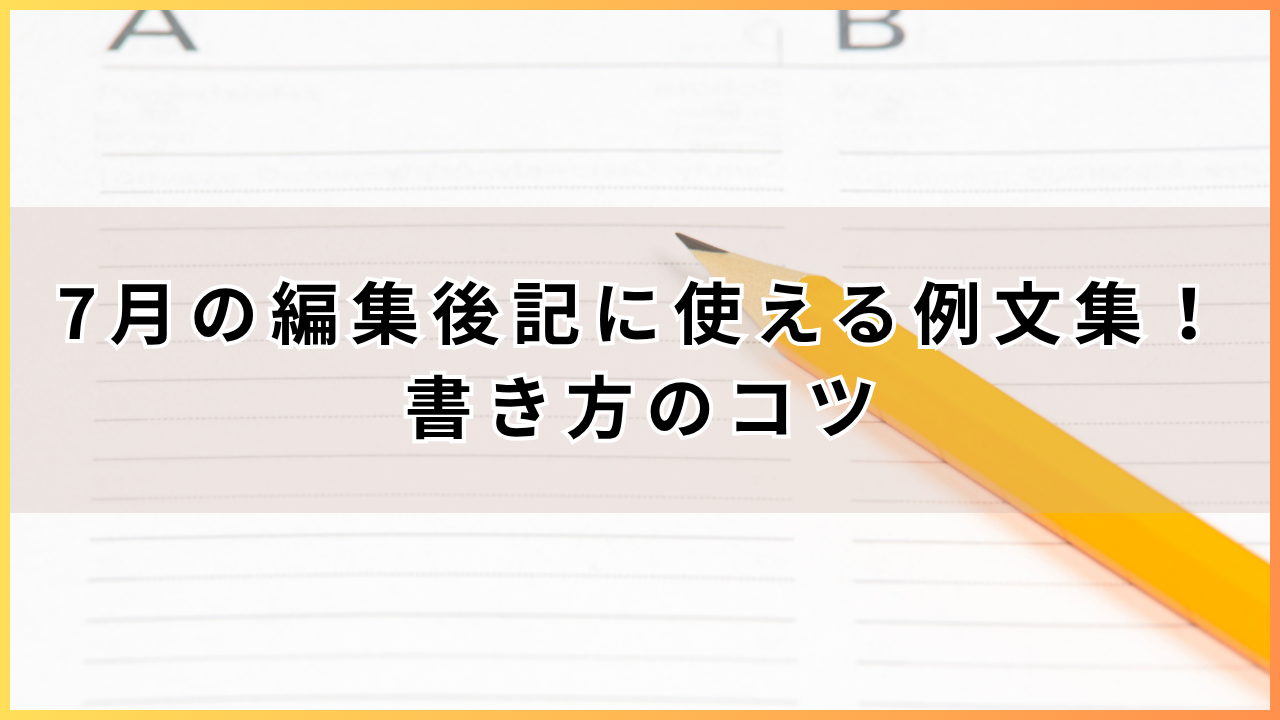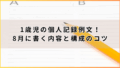7月は梅雨明けから夏本番へと移り変わる季節です。
編集後記でも、この時期ならではの空模様やイベントを取り入れることで、読者に季節の息吹を感じてもらうことができます。
しかし「何を書いたらいいのかわからない」「例文を参考にしたい」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、7月の編集後記にすぐ使える短文例文から、誌面にそのまま載せられるフルバージョン例文まで幅広くご紹介します。
さらに、文章を彩るためのキーワードリストや、五感を使った表現・エピソードを交えた書き方のコツ、近年注目されているトレンドもわかりやすく解説。
この記事を読めば、7月にふさわしい編集後記がすぐに書けるようになるはずです。
ぜひ参考にして、あなたらしい言葉で季節感あふれる編集後記を仕上げてみてください。
7月の編集後記とは?
7月の編集後記は、夏の始まりを彩る話題を取り入れながら、読者に親しみを持ってもらうための大切なコーナーです。
ここでは、編集後記そのものの役割と、7月ならではの季節感をどう活かせるのかを整理していきましょう。
編集後記の役割と魅力
編集後記は、雑誌や広報誌の最後に置かれる「ちょっとしたつぶやき」のような存在です。
取材の裏話や感じたことを共有することで、記事の締めくくりとして温かみを添える役割を持ちます。
読者と編集者をつなぐ架け橋になるのが、編集後記の一番の魅力です。
| 特徴 | 編集後記の役割 |
|---|---|
| 文章の長さ | 短くシンプルにまとめる |
| 内容 | エピソードや季節感を交える |
| 目的 | 読者との距離を縮める |
7月ならではの季節感や話題性
7月は、梅雨明けから真夏への移り変わりを感じられる季節です。
編集後記でも、空の青さや入道雲、夏祭りや七夕などのイベントをテーマにすると、自然と季節感が出せます。
同じ7月でも前半と後半で雰囲気が変わるので、その時期に合わせた話題を選ぶとよりリアルな印象になります。
例えば、7月上旬なら「梅雨明けが待ち遠しい」という表現、下旬なら「夏の夜空に大輪の花火が咲いた」という表現がぴったりです。
7月の編集後記におすすめのテーマ
7月の編集後記では、季節を感じられる話題を選ぶことがポイントです。
同じ夏でも、行事や自然の移ろいを切り取ることで、読者の共感を得やすくなります。
ここでは、特に取り入れやすい3つのテーマをご紹介します。
夏祭りや花火大会を取り入れる
7月といえば、街を彩る夏祭りや夜空を飾る花火大会です。
賑やかな空気感を文章に織り込むと、読者に夏らしさを届けられます。
音・光・にぎわいをキーワードにすると、情景が浮かびやすくなります。
| テーマ | 表現のヒント |
|---|---|
| 夏祭り | 屋台の香り、太鼓の音、浴衣姿の人々 |
| 花火大会 | 夜空に咲く大輪、胸に響く音、歓声 |
梅雨明けや真夏の暑さを描写する
7月は梅雨明けを迎える頃で、空や風の変化が印象的です。
入道雲や強い日差しを描くことで、季節感を自然に取り込めます。
「梅雨明けの青空」「夏の日差し」などは、文章を鮮やかに彩るフレーズです。
| 場面 | 表現例 |
|---|---|
| 梅雨明け | 「ようやく空が晴れて、真っ青な夏空が広がりました」 |
| 真夏 | 「セミの声がにぎやかで、夏の訪れを全身で感じます」 |
七夕や家族の思い出を盛り込む
7月7日の七夕や、家族との思い出も人気のテーマです。
願いごとを短冊に託すシーンや、子どもとの夏のひとコマを描くと、温かい雰囲気になります。
小さな出来事でも「特別な瞬間」として表現すると、読者の心に残りやすいです。
| テーマ | 例文フレーズ |
|---|---|
| 七夕 | 「星空を見上げながら、短冊に書きそびれた願いをそっと心に描きました」 |
| 家族の思い出 | 「夕暮れに庭でシャボン玉を飛ばす時間が、何よりの夏の楽しみです」 |
7月の編集後記に使える短文例文集
ここでは、すぐに使える短めの編集後記例文をご紹介します。
読者に軽やかに読んでもらえるよう、3〜5文程度のシンプルな文面を集めました。
季節のあいさつ、イベント、日常の一コマと、幅広いテーマでまとめています。
季節のあいさつを中心にした例文
「梅雨が明けて、青空のまぶしさに夏の訪れを感じています。皆さまはいかがお過ごしでしょうか。どうぞ体調に気をつけて、元気に7月を楽しんでください。」
「セミの声が朝のBGMになり、いよいよ夏本番ですね。冷たい麦茶が手放せない日々です。皆さまも涼を感じながらお過ごしください。」
「強い日差しに驚きつつも、夏の鮮やかな景色に心がわくわくしています。今月もどうぞよろしくお願いいたします。」
| シーン | 短文例 |
|---|---|
| 梅雨明け | 「空の青さに、思わず深呼吸したくなる季節ですね。」 |
| 真夏 | 「夏空に大きな入道雲が広がり、心まで晴れやかになります。」 |
夏のイベントを題材にした例文
「久しぶりに花火を見上げました。夜空に咲く光の花が、心に残る夏の思い出を作ってくれました。」
「地元の夏祭りに行きました。屋台の香りや太鼓の音に包まれて、子どもたちの笑顔に元気をもらえた気がします。」
「7月7日の夜、短冊には書けなかった願いを星空にそっと託しました。小さな行事でも心が温かくなりますね。」
| テーマ | 短文例 |
|---|---|
| 花火 | 「夜空に広がる光に、思わず見とれてしまいました。」 |
| 夏祭り | 「にぎやかな音と色に包まれて、夏の楽しさを実感しました。」 |
暮らしや日常を取り入れた例文
「朝顔が花を咲かせるたびに、夏の訪れを実感しています。小さな自然の変化が、毎日の楽しみになっています。」
「最近、家庭菜園のトマトが赤く色づきました。日々の成長を眺めるだけで元気をもらえます。」
「涼しい風を感じながらの夕暮れ散歩が、ささやかな楽しみになっています。夏のひとときに癒やされますね。」
| テーマ | 短文例 |
|---|---|
| 植物 | 「庭のひまわりが空に向かって咲き誇り、夏を象徴してくれています。」 |
| 日常 | 「夕暮れに聞こえる風鈴の音に、心が落ち着く時間を感じます。」 |
7月の編集後記フルバージョン例文集
ここでは、実際の誌面や社内報などにそのまま使える、200〜300字程度のフルバージョン例文をご紹介します。
短文では表現しきれない臨場感やストーリー性を持たせることで、読者により深く共感してもらえる文章になります。
家族旅行をテーマにしたフルバージョン例文
先日、家族で海へ出かけてきました。波打ち際ではしゃぐ子どもたちの姿を見ていると、自分もつい童心に返ってしまいます。空の青さと潮風の香りに包まれながら過ごす時間は、まるで日常を忘れさせてくれる特別なひとときでした。普段は慌ただしく過ぎてしまう毎日ですが、自然と触れ合うことで心も体もリセットできたように感じます。皆さまも、この季節ならではの体験を見つけて、穏やかな7月をお過ごしください。
夏祭りや花火をテーマにしたフルバージョン例文
久しぶりに地元の夏祭りに参加しました。夕暮れとともに灯る提灯の明かり、にぎやかに響く太鼓の音、漂う屋台の香り。五感を刺激する夏の風景に囲まれて、自然と笑顔になれました。そして夜空に広がった大きな花火は、言葉にできないほどの迫力で胸に響きました。ひとつひとつの瞬間が、夏の思い出として心に刻まれていきます。読者の皆さまにも、この季節ならではの景色が素敵な思い出となりますように。
七夕や星空をテーマにしたフルバージョン例文
7月7日の夜、ふと空を見上げると、星がいつもより明るく輝いているように感じました。短冊に願いを書くことはできませんでしたが、静かに心の中で思いを託してみました。七夕はほんの一日だけの行事ですが、夜空を見つめる時間は心を落ち着けてくれる特別なものです。慌ただしい日々の中でも、こうした小さなひとときを大切にしていきたいと思います。皆さまの願いも、どうか届きますように。
| テーマ | フルバージョンの効果 |
|---|---|
| 家族旅行 | ストーリー性があり、読者に共感を生む |
| 夏祭り・花火 | 臨場感が強く、季節感を最大限に演出できる |
| 七夕・星空 | 静かな余韻を残し、読後感を深める |
7月の編集後記を書くコツ
7月の編集後記は、短い文章の中に「夏らしさ」と「人柄」をにじませることが大切です。
ここでは、誰でも取り入れやすい3つのコツをご紹介します。
五感を活かした言葉選び
視覚・聴覚・嗅覚・触覚を使った表現は、文章に臨場感を与えます。
例えば、「セミの声が響く朝」「風鈴の音に涼を感じる夕暮れ」などは、読者が実際にその場にいるような気持ちになれます。
五感を描写することで季節感がぐっと強まるのです。
| 感覚 | 表現例 |
|---|---|
| 視覚 | 「入道雲が空いっぱいに広がっていました」 |
| 聴覚 | 「セミの鳴き声が一層にぎやかになってきました」 |
| 嗅覚 | 「風に乗って甘い朝顔の香りが漂ってきます」 |
エピソードを交えて親しみを出す
編集後記にちょっとしたエピソードを盛り込むと、読み手は自然と親近感を抱きます。
例えば、「家庭菜園のトマトが色づきました」「子どもと一緒に夕暮れ散歩を楽しみました」など、身近な話題が効果的です。
小さな出来事でも“自分の言葉”で綴ることが大切です。
| テーマ | エピソード例 |
|---|---|
| 家庭 | 「朝顔の花が一斉に咲いて、子どもと一緒に写真を撮りました」 |
| 日常 | 「夕暮れ時の散歩が、1日の楽しみになっています」 |
短くリズムよくまとめる方法
編集後記は長文にする必要はありません。
むしろ短文でリズムよく区切った方が、読みやすさが増します。
一文を短めにして改行を多めに使うのがポイントです。
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| 短文を意識 | テンポよく読める |
| 改行を入れる | 視覚的に読みやすくなる |
| やさしい言葉 | 親近感が生まれる |
7月の編集後記に役立つキーワード集
編集後記をスムーズに書くためには、季節感を引き出すキーワードをストックしておくのが便利です。
ここでは、7月らしい挨拶や風物詩、日常で使える表現をカテゴリー別に整理しました。
時候の挨拶に使える言葉
7月の冒頭に使いやすいのが「時候の挨拶」です。
手紙の書き出しのように取り入れると、文章がきれいに始められます。
季節の始まりを感じさせるフレーズを活用しましょう。
| シーン | キーワード例 |
|---|---|
| 7月上旬 | 梅雨明け、夏至の頃、七夕の季節 |
| 7月中旬 | 盛夏、入道雲、真夏の青空 |
| 7月下旬 | 蝉しぐれ、酷暑、夏の夕立 |
夏の行事や風物詩の言葉
7月には、誰もが思い浮かべるイベントや風物詩があります。
これらを文章に取り入れると、一気に夏の雰囲気が広がります。
行事と自然をうまく組み合わせると表現の幅が広がります。
| カテゴリ | キーワード例 |
|---|---|
| 行事 | 七夕、夏祭り、花火大会 |
| 自然 | ひまわり、風鈴、入道雲 |
| 風物詩 | 金魚すくい、かき氷、蝉の声 |
生活に寄り添うフレーズ
季節の中での「日常のひとコマ」を描くと、読者に親しみを持ってもらえます。
例えば、朝顔や麦茶といった身近なモチーフは、暮らしの温かさを伝えるのにぴったりです。
生活感のある言葉は読者の共感を呼ぶので、ぜひ活用しましょう。
| シーン | キーワード例 |
|---|---|
| 家庭 | 朝顔、家庭菜園、夕涼み |
| 食べ物 | かき氷、スイカ、麦茶 |
| 暮らし | 団扇、扇風機、打ち水 |
近年の編集後記トレンドと工夫
編集後記は時代とともにスタイルが変化しています。
近年は、読者が親しみを感じられる短く印象的な文章や、デジタル媒体に合わせた工夫が注目されています。
ここでは最新のトレンドと、その取り入れ方をご紹介します。
SNS時代に好まれる短く印象的な文
スマートフォンで読む人が増えたことで、編集後記も短めで読みやすいスタイルが支持されています。
長く説明するよりも、一言で心に残る表現が効果的です。
例えば、「夏の夜風が心地よく感じられる頃となりました。」といったシンプルな一文でも十分に魅力を伝えられます。
| 従来の文例 | 現代的な文例 |
|---|---|
| 「梅雨が明け、夏の訪れを告げる季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。」 | 「梅雨が明けて、空の青さが一段と鮮やかになりました。」 |
オンライン発信で映える工夫(写真・絵文字)
紙面の編集後記では文字が中心ですが、デジタル発信なら写真や絵文字を添えるのも一案です。
例えば、花火やひまわりの写真を加えるだけで、季節感が一気に広がります。
ただし使いすぎず、文章を引き立てる程度にするのがコツです。
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| 写真 | 視覚的に季節感を補強できる |
| 絵文字 | カジュアルな雰囲気を演出できる |
AI活用で表現を磨く方法
近年は、AIを使って文章のアイデアを広げたり、言い回しを工夫する人も増えています。
ただし大切なのは、自分の言葉として仕上げることです。
AIの提案をヒントにしながら、自分らしさを加えることで、よりオリジナルな編集後記が完成します。
| 活用方法 | メリット |
|---|---|
| 文章の構成を参考にする | 短時間で下書きができる |
| 表現のバリエーションを増やす | 語彙の幅が広がる |
まとめ:7月の編集後記を魅力的に仕上げるために
7月は、梅雨明けから夏本番に移り変わる季節です。
編集後記では、その移ろいを文章に取り込み、読者に親しみを感じてもらうことが大切です。
ここまでご紹介した例文やコツを押さえれば、誰でも魅力的な一文を綴ることができます。
ポイントは「季節感」「身近なエピソード」「読みやすさ」の3つです。
夏祭りや花火大会といった行事、家庭や日常の小さな出来事を選ぶことで、自然と人柄も伝わります。
また、短文でリズムよくまとめると、スマートフォンで読む読者にもやさしい文章になります。
| 要素 | 活かし方 |
|---|---|
| 季節感 | 時候の挨拶や夏の行事を入れる |
| 身近なエピソード | 日常や家族のひとコマを描く |
| 読みやすさ | 短文+改行でテンポよく仕上げる |
7月の編集後記は、夏らしい雰囲気を伝えるだけでなく、読者との距離を縮める大切な場です。
あなたらしい言葉を大切にしながら、今月ならではの思いを自由に表現してみてください。
きっと読者の心に残る、温かみのある一文に仕上がるはずです。